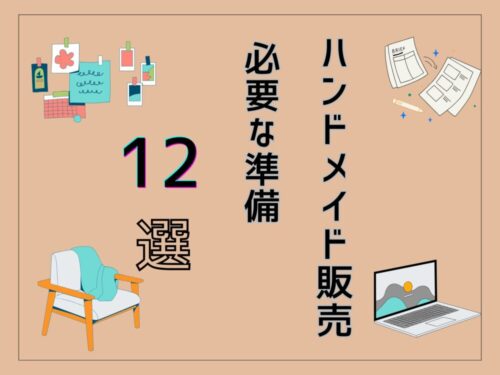「工具なんて使えたらなんでもいいよ」
最初は僕もそう思っていた。
でもちょっといい工具を使ってみたら「もう戻れない、、、」ってくらい違いを感じる。
異世界転生して無双気分を味わいたい人におすすめしたい。
それぐらい違いがあって、作業スピード、作りやすさが桁違いに変わるので、ぜひいい工具を見つけてほしい。
そう言いつつも最初は100均工具をおすすめする。
ハンドメイドが続くか分からないし、作業自体が不要になったりすることがあるからだ。
なので必要になったら、ちょっといい工具を買えばいい。
今回紹介するのはアクセサリーや雑貨など比較的小さなものを作るときの工具になる。
工具以外で必要なものは別の記事で紹介しているので、ぜひあわせて読んでほしい。
目次
オススメ工具 一覧
この4つは基本的にどんなジャンルの作家さんでも必要になると思う。
試しにハンドメイドを始めるひとは100均で揃えても全然OK。
使用頻度が高くなってから、いい工具を買い直しても遅くはない。初期投資して使わなかったらもったいないからね。
100均 ニッパーは使える?
使える!
ニッパー、ペンチ(ヤットコ)、ピンセットなどは100均で揃えよう。
まずは100均で揃えよう。
初心者の段階では必要な工具の機能がわからない。
なので作品作りに慣れて、必要な機能を理解してから高い工具を買おう。
でも高い工具はやっぱり使いやすい。手になじむし、疲れにくい。
各工具の選び方や特徴をまとめてみたので参考にしてほしい。
1.ニッパー

細い針金、チェーン、ワイヤー、金具なんかを切断するときに使うニッパー。
ニッパーは用途ごとに選ばないと、刃先がすぐにダメになる。
そして大きいニッパーのほうが圧倒的に切る力が強いので、手が疲れにくい。
でも細い針金や電線などを切るときは小さいニッパーが使いやすい。
使用頻度に合わせて選んでほしい。
最終的には2~3種のニッパーを持つことになると思う。
切断する素材と大きさ
まずは切断する素材にあったニッパーを選ぼう。
プラスチック専用があるので注意しよう。金属を切ると一発で刃先がダメになる。
小さめの金具・針金・配線・プラスチックなんかだと、ミニチュアニッパー、精密ニッパーと呼ばれる小さめのニッパーを使おう。
チェーンや太い絶縁電線、樹脂の棒なんかを切断するときは単純にニッパーと呼ばれたり、強力ニッパーって言われるサイズのものを使う。
刃先の形状
次に選ぶのは、刃先の形状。
使い心地に直結するので慎重に選んでほしい。
刃先は2種類あって、ラウンド刃(曲がり)or フラット刃(平ら)のどちらかだ。
一般的にはラウンド刃(曲がり)がスタンダードな形状で、硬いモノを切るのに適している。
対してフラット刃(平ら)は、切断面を平らにできて小さな力で切れる。
詳しくは工具メーカーのツノダさんのHPを読んでみてほしい。すごく分かりやすい。
ニッパーの使用感
ちなみに僕は合計3を使い分けている。
銅線、小さい金具、針金、プラスチック

ラウンド刃。銅線、細めの電線、小さな金具、細い針金に使っている。
めちゃくちゃ切れやすくて、小さいので使い勝手が抜群にいい。
使用頻度は圧倒的に多くて70%以上はこのニッパーと使っている。
プラスチックをきれいに切るとき

フラット刃。樹脂の平面が必要な場面、切るのが快感になる。プラスチック限定だけど。
使用頻度は低め。切れ味が命なので大事に扱おう。
ざくざくなんでも切るとき

何でもザクザク切るときによく使う。
ラウンド刃、太いリード線、絶縁電線、チェーン、金具、なんでも切れる。
刃を広げる用のスプリングがついてないので、細かい作業なんかには不向き。
使用頻度は ① > ③ >> ② って感じ。
ラウンド刃はザクザク使うのでリーズナブルな価格帯を選んで、フラット刃はここぞというときに使うのでお高めを選んでいる。
①③なんかは5年以上使ってるけどまだまだ現役。
このニッパーだけは100均ではなくて、ちゃんとしたメーカー品を早めに揃えよう。
100均ニッパーはサビるのが早くて、すぐに切れなくなるからだ。

切れ味が悪いと力が異常なほど必要になるし、何より切断面が汚くなってしまう。
なので、切れ味長持ちのニッパーをおすすめする。刃の素材と表面処理が違うので全然長持ちする。
あと、グリップ部分。
100均ニッパーはグリップ部がすぐにとれるし、使い心地がいまいちなので長時間使うときは手の筋肉が悲鳴を上げる。
その日はほかの作業ができなくなるくらい。
グリップの色が違うだけで1,000円くらいで売ってたりするので注意してほしい。
メーカーは、ツノダ、HOZANホーザン、Engineerエンジニア、KTC京都機械工具なんかをおすすめする。ほかにも優良メーカーはたくさんあるので、ぜひ調べてみてほしい。
気に入った色の工具を選ぶのも悪くはないけど、長く快適に使うなら優良メーカー品をおすすめする。
2.ペンチ(ヤットコ)

ペンチ、ヤットコと呼ばれる、掴むことに特化した工具。
ペンチは先っぽがギザギザ、ヤットコはつるっと平坦なものだとか切断刃の有無で分類されたりしてるけど、あんまりピンとこない。
僕が使ってるミニチュアラジオペンチは、先端が平坦で切断刃もないけど、商品名は立派にペンチで売られている。
どっちの呼び名でもいいけどね、使えれば。
ペンチも使用頻度が高い必須工具だ。
ペンチも用途によって使い分けが必要で、結局は形状の違うペンチを数本持つことになる。
掴む部品の大きさ
まずはペンチの大きさを選ぼう。
これはニッパーと同じで、掴む部品の大きさによって選ぶ。小さい部品を大きなニッパーで長時間掴むと指がもげる。
逆でも指がもげる。その日は手作業ができないくらい疲れる。
先端形状
次は先端の形状で選ぼう。
アクセサリー関係や小物雑貨の場合は、部品に傷がつかないように先端が平らなペンチがメインになると思う。
あと丸ヤットコと呼ばれる先端がお箸のように円柱になっているものも使うと思う。
ワイヤーや金具をきれいに丸める便利な工具だ。
もうちょっと雑に扱えるシーンでは、先端がギザギザしてグリップ力のあるラジオペンチになる。
ペンチの使用感
僕はペンチは合計4種使っている。
小さいものと掴むとき

ほとんどこれを使っている。針金、金具、繊細な部品をつかむのに最適。バネがついてて、手がつかれない。バネもなくならない。
大きめのものをつかむとき

ちょっと大き目な部品、金具を曲げるときに使う。ニッパー部はまあ使わない。ギザギザがついてるので力強く使える。
細かな部品には不向き。先端のギザギザもあるのでキズが付きやすい。
力強くつかむとき
③ペンチ ノーブランド
力仕事担当、DIY用、人間の力では出せないピンチ力を発揮する強いやつ。

使用頻度は ① > ② > ③
正直ペンチは100均でも全然いいと思う。
サビやすいけど、ニッパーほど影響はない。壊れやすさと、使いにくさに目をつむれば全然使える。
おすすめのメーカーはニッパーと同じでツノダ、HOZANホーザン)、Enginerエンジニア、KTC京都機械工具あたり。
買い替え時期が来たら検討するでも全然OK。
3.カッター、アクリルカッター
紙を切る、袋を開ける、接着剤を削る、樹脂を削る、印をつける、結構使うカッター。
でも一般的なカッターでOK。小さいカッターだけでも十分やりくりできる。
厚いアクリル板を切るときなんかはアクリルカッターが必要だけどね。
有名なのはこれ。
4.ピンセット

個人的に値段でかなり違いがある工具だと思う。
使いやすさと耐久性が全然違う。
100均ピンセットではすぐに先端が変形して、掴みにくくなる。
それに同じ100均でもピンセットの掴みやすさに当たりはずれがあって、外れのときはほんとに小さいモノがつかめない。
作業効率に直結する工具だ。ぜひいいものを見つけてほしい。
先端の形状
選び方なんだけど、先端の形をメインに選ぼう。
ストレート、先細、つる首、先平なんかの形状が一般的で、掴む部品に合わせて選ぶことになる。
個人的に数mm~3cmくらいまでの小さな部品には、先端が少し曲がっている「つる首」ピンセットが使いやすいと思う。
ストレートタイプでもいいけど、モノをつかむときに角度をつけなくちゃいけなくて、手を動かす範囲が広くなりがちだ。
小さな部品をつかむために手を大きく動かすのがしんどいので、動きを小さくできるつる首タイプを使っている。
ちょっと力のいるシーンでは少し大きめのストレートタイプを使うこともある。
ピンセットの材質
次に選ぶのは、ピンセットの材質になる。
ステンレス(SUS)が一般的だと思うけど、竹、樹脂のピンセットもある。
竹ピンセットは傷を付けたくない電子部品、レンズなんかを扱うときに使う。絶縁性が良くて、磁性を持たないので静電気が起きないことも特徴だ。そしてなにより軽い。
樹脂ピンセットも竹ピンセットと特性は似てるので、好みでいいんじゃないかな。竹のほうが少しお高めのイメージがある。
おすすめのメーカーはアネックス、HOZAN、エンジニアとかになる。ニッパーやペンチを扱うメーカーさんならピンセットも扱ってるので、一緒に探してみてほしい。
ピンセットの使用感

ANEX ステンレスピンセット 先細鷲型115mm (SUS304)
めちゃくちゃ使いやすい。ほんとにおすすめ。
1mmくらいの部品も全然持てる。手がつかれない。
ピンセットを落とすと先端が曲がってしまうので注意しよう。
まとめ
最初にそろえる工具はこの4つでいいと思う。
後々必要になる工具は延々と出てくるけど、これだけあれば基本的な加工はできる。
困って必要に迫られてから買い足すでいい。実際、工具は現在進行形でどんどん買い足している。
ハンドメイドのジャンルで必要とする工具は異なるし、個人によっても使う道具が全然違う。
なので、「これが正解」っていう工具はないと思う。